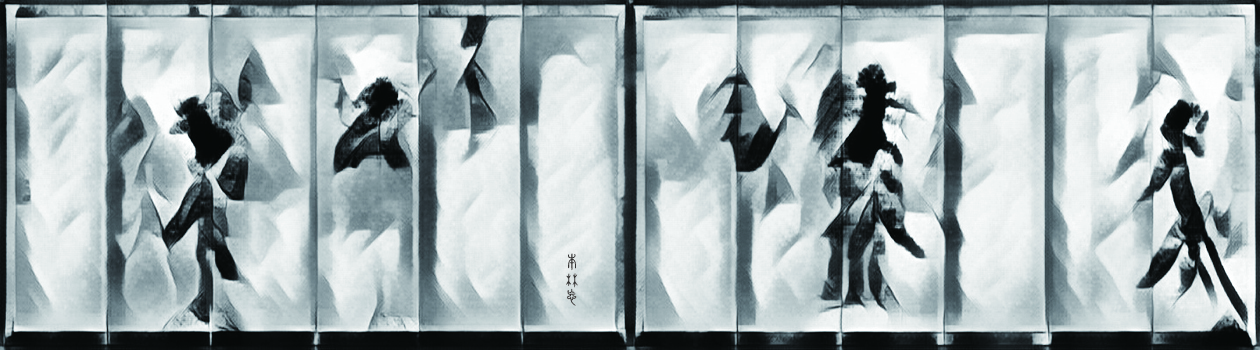蟷螂は夢を見た それはまるで果てることのないうたで はじまりも終わりもなかった ただ風のようにとうとうと流れ あらゆるものをつつんでいた 夢のなかではまだ月が昇っていた 月が昇らなくなって久しく もう月のことも忘れかけていた 夢のなかの月は 地を見張る目のようだった そこに狂いはないか そこに罅割れはないか じっと見据える冷たい目だった 幾度となく月の検分を受けたが それは煩わしくもありながら また検分を待ち焦がれるような 不思議な面持ちだった 月はいつも三角形めいて映ったが たぶんそれは真珠のように丸いのだろう そのどこまでも透きとおった目で いつも地を射抜いていた そんな月がある日ふいに昇らなくなった いったいなぜ隠れてしまったのか 蟷螂にも知る由もなかったが それから地はたださびれていった 獣や虫たちもしだいに姿を消し 草や花や木もしだいに枯れ いまでは化石のように沈黙した残骸が転がっているだけだった それでもなお蟷螂は変わらず森を彷徨っていた 雨上がりの水滴に 自分の姿が映ったことがある たよりない三角の顔がどこか月めいていた いまも自分はここに存在しているのか それともとうに朽ちていて あてのない思い出ばかりが漂っているのか そのとき ふいに雲間から一条の光がもれた 刹那のことであったが月であったような気がした だが地に自分の影は映らなかった すでに思い出ばかりとなっているのやもしれぬ そろそろお暇をいただきたいとも思うが もうここには何もない ただ無だけがぶっきらぼうに投げ出されている
森の王
石がひとつ転がり 夜がひとつ弾けた 王は真紅のガウンを纏い 蔓で編まれた王冠を被り 森のなかを巡回する 夜の巡回はすっかり日課となっていた この森は王国の領土であり 城でもあった この王国がいったいいつ建国されたのか 記録に定かではないが 王冠とガウンを引き継ぐ儀式だけは 厳格に伝えられていた もう百年ほど前のことだが 旅の途中でこの森を通りかかったとき 泉のほとりで休んでいると どこからともなく ひとりの男があらわれた 男はおよそ森には不釣り合いの真紅のガウンを纏い 王冠を被っていた そして久し振りに人にあったので是非歓待したい 旅の土産話でも聞かせてもらいたい とのことで 森の奥へ案内された そこには巨大なキスカヌの木が聳え 男はそのウロへ入っていった 男に案内されるままに木のウロに入ると まずここで着替えをといわれ 男にいわれるままに服を交換した そして宴の支度があるのでしばしここでお待ち願いたいと言い残し そのまま男はウロを出ていった しばらく待っていたが男は一向に帰ってくる様子もない これでは日が暮れてしまうと思い ウロを出て 男を探しに出掛けた だが どこを探しても男の姿はなかった 仕方がないのでこのまま森を出て次の町へ行こうと森の出口にさしかかったとき 体が石のように固まり どうにも動けなくなった 少し引き返すと体は動く だがまた森の出口にさしかかると体はまたしても石のように固まった 何度やっても同じだった 王冠をはずし ガウンも脱ぎ捨てようとしたが 王冠もガウンも体の一部になったかのようにびくともしなかった あたりが暗くなってくる とりあえず一度キスカヌの木のウロへ戻ることにした ウロに戻ったが やはり男の姿はなかった ウロのなかはぼんやりとした青白い光につつまれていた どうやらウロのなかに生えている苔が発光しているようだった ウロのなかに一冊の古い書物が置かれていた 書物を開くと見たこともない文字が並んでいたが 文字を目で追うと 書かれている内容が頭に浮かんだ 森の王国の巡回のこと 戴冠の儀のこと キスカヌの木のこと などがつらつらと書かれている どうやら森で出会った男との服の交換は 厳粛なる戴冠の儀だったらしい 王冠を戴いたものは 次の戴冠の儀まで森の王でいなければならない それまでは王冠を外すことも 森の王国から出ることもかなわない あの男は 毎日森に迷うものを求めて巡回をつづけていたわけだ あれから百年経っても 誰ひとりとして森にやってこない 老いることもなく森の巡回を繰り返しても ずっと何も変わらない 森は相変わらず森だった 何のためにこの森を通りかかったのかも忘れかけていた もともと目的などなかったのかもしれない ある朝 キスカヌの木の葉が一枚落ちていた この森の王になってからはじめてのことだった キスカヌの木の葉を拾い それがまるで儀式でもあるかのように 書物に栞のように挟んだ あくる朝 キスカヌの木の葉が二枚落ちていた 何かの前触れのようだった そのあくる朝は四枚 そのあくる朝は八枚 というように落ちる葉は増えていった 巡回していると いたるところで木も草も枯死していた ある朝 キスカヌの木の葉を掃き集めていると 頬に痛みをおぼえた そっとさすってみると 皮膚がぼろぼろと剥がれ落ちた 枯死がひろがるにつれ 体がぼろぼろと崩れ落ちていく ある新月の夜 残っているのは左足のかかとだけになり もう歩くための足もなかった 森の王国もすっかり透明な灰になっていた そしてそのあくる朝 左足のかかとも崩れ落ち 透明な灰のなかに紛れていった 森の王国は誰にも知られない
鈴と沈黙
ある夜 少しだけ開けられた窓から 鈴の音が聞こえてくる 鈴の音がしだいに近づいてくる どこからかやって来た巡礼団かとも思ったが こんな夜半に歩くとも思えない いったいどこから聞こえてくるのだろうと 窓を開け 辺りを見渡す 遠くで蛍の光のようなものがゆらめいたかと思ったが すぐ消えてしまう 鈴の音はさらに大きくなってくる 声明ともことなるざわめきもひろがっている ふいに目の前に鈴があらわれ りん と鳴る まわりで影が蠢いている もう一度鈴がりんとなったとき 思わず体が吸い寄せられ 窓の外にそのまま飛び出してしまう 気がつくと 鈴の後について町の上空を飛んでいた 声がでない 周りを見ると 同じように無数の人が飛んで雲のようになっていた 声明とも思った音は 無数の人が大気と擦れあう音のようだった 引き返そうとも思ったが 体はそのまま雲を離れようとはしなかった 雲はしだいに膨れあがっていく いまいったいどこを飛んでいるのだろう なんだか地上が騒がしい 祭りかとも思ったが どうも戦争のようだ あちらこちらで火の手があがり 銃声や砲声 爆発音がしている それでも鈴は飛びつづける 気がつくと雲はさらに膨れあがり 血を流すものや 手足を失ったものが雲に加わっている 鈴が進むにつれ 地上がしだいに静かになっていく 戦火もおさまり 銃声もしなくなる そして地上はただ夜につつまれる それでも鈴はなおも進んでいく いまはいったいどこを飛んでいるのだろう やがて夜が白んでくる 眼下に大きな川と密林がひろがっている 鈴の音が鳴る 雲はさらに膨れ 虫や鳥 けものや花や木や魚が加わる みな鈴の後を追い 雲となって飛んでいる 鈴はなおも飛びつづける すでにこの星を何周か飛んでいるのだろう 幾つもの夜と 幾つもの昼がすぎていく すでに雲は星にかかる輪のようになっている 雲のなかにいいようのない無常感がひろがる 無常の輪がこの星にかかっている これは葬列なのかもしれないな そう思ったとき ひときわ高く鈴が鳴る 海が朝焼けに染まっている ふいに雲が真っ逆さまに下降をはじめる どうやら鈴が海めがけて急下降しているようだ みるみるうちに海面が迫り来る ああ このときが来たのだな そう思ったとき 海に飛びこんだ 雲はなおも海の底めがけて進んでいく りん と鈴が鳴る 七ツ鳴ったとき 雲の動きがぴたりと止み 光もない空間に ただアルトーの沈黙だけがひろがっている
夜は名前をもたない
夜は名前をもたない 夜という物質があるわけではなく ただそこに在る物質たちが夜として響きあう 意味も秘密もない響きのなかで 物質たちは夜を慈しみ 夜をガウンのように纏う 名前の与えられたあらゆる物質の隙間に 夜は漂い 世界の消息に耳を澄ます 二十三街区の地図にもない路地に 名前をもたない影がひとつ 佇んでいる 何か目的のあるわけでもなく 何か思い出のあるわけでもなく ただ耳を澄ませている 夜が何かのはずみに形象化したものかとも思ったが それにしてはあまりにたよりない 死に損なった民俗学者かとも思ったが それにしては目がどんよりしている 通りかかった黒猫が怪訝そうに影を見上げ 尻尾を立てて ゆっくりと過ぎていく どこからかうたが聞こえてくる 窓という窓はどこまでも暗く ラジオの音にしてはあまりに澄んでいる やがてうたの止むとき はじめからなかったかのように 影のすがたも消える 物質たちのあいだにざわめきがひろがる 記憶が物質化しつつあるのか 物質が記憶化しつつあるのか どこかでアーカーシャの擦り切れる音がする もう地上に音楽家はいない 最後に残された黒猫が夜の見回りを終え にゃあとひと啼きすると 小さな記憶をしのばせて夜の奥に消える 夜がしだいに結晶化をはじめる 結晶化といっても物質化ではなく 限りなく無に溶けこんでいく 夜は名前をもたない 夜という物質があるわけではなく ただそこに在る物質たちが夜として響きあう
無の書物
目が覚めると 雑然とした机の上に無の書物が置かれている それはまるで宇宙創生のときからそこに在るようで 圧倒的な存在感が光を放っている いまにも崩れてしまいそうな頁に 見たこともない 不揃いの文字が連綿と並んでいる 海の飛沫のような文字はあらゆる方向に連なっていて いったいどのように文字を追えばよいのか 皆目見当がつかない 頁を捲ろうとすると 指先は虚しくも空をつかみ 春の野に取り残される すでにそこにすべての記憶と記述が宿っているのに けしてそれに触れること それを読むことはかなわない それなのに それから目を離すことができない ふと目を離した隙に 砂糖菓子のように消えてしまいそうで ただこどものように空気の隙間で怯える ふいにこどもの頃の記憶が蘇り 思わず目を離しそうになる 縁日の屋台から屋台へと巡っているうちに しだいにあたりは寂れ いつのまにか 風の吹き荒ぶ廃屋の前に佇んでいる 帰り途もわからず ただ出鱈目のうたを口ずさみながら震える足を一歩 また一歩送りだすように歩いていく 遠くに灯りが見える たよりない灯りはゆらめきながら夜の奥に文字を綴る 何かに躓いて倒れそうになる からだを起こしながら足元を見ると草が結ばれている そうだ ずっと前にかくれんぼをしていたときに結んだものかも知れない かくれんぼはいまもつづいているのだろうか ふいに寂寥感におそわれその場に蹲る はらってもはらっても消えない夜が降ってくる 風のなかに頁の捲れる音が呟きのように響く 気がつくと机の脇に佇んでいる 机の上は雑然としていて 書きかけの原稿用紙が眠たそうに横たわっている 窓から風が入ってきて頬を撫でる 心の奥の箪笥から 何かが持ち去られてしまったような気がするが いったいそれが何であるかわからない 読みかけの本があったような気がするが いったいそれが何の本であるのか さっぱり思い出すことができない きっと記憶など 生まれたときから持ってはいない ただ無の粒子として誰に知られることもなく ここに在る
四ノ森
この伝説の森にはあらかじめすべての文字が象られ 枝先や葉裏にしまわれていた 歴史も思い出もまた記憶ばかり 文字を辿れば 過去から未来まで すべての歴史を読み解くことができる あらゆる記憶が 人の欲のままに造られる この森を抜けるもの あるものは狂喜し あるものは絶望し あるものは安堵した だが この森に入ったものはひとりとして出てこなかった それでこの森は四ノ森とも呼ばれていた ある玄月の夜 からだ中傷だらけの男が森にやってきた 男は近くの村へ旅に来ていた作曲家で 夜半すぎ 空襲警報で目を覚ました 宿は爆撃を受け 消失してしまった 夜空が紅蓮に染まっていた そして片足を引き摺りながら 地図にもない森まで逃れてきた 森のなかは静まり返っていた 空襲警報も 戦闘機の爆音も 銃声も聞こえなかった いったいこの森は誰にも見えないのだろうか すぐ近くが戦場であるとはとても思えない ただ静寂だけがひろがっていた 男はしばらくからだを休めていたが やがて近くに落ちていた枝を杖がわりにして森の奥へとぼとぼと歩んでいった 枯葉を踏みしめる音だけが響くなか 男の脳裏にさまざまな光景が浮かんだ 病院から抜け出して旅に出る前 男は鯨になってひとり暗い海のなかを泳ぐ夢を見ていた いま男は鯨になっていた 森のなかを泳いでいくと さまざまな夢を見た ふいに男は立ち止まり 後ろを振り返ったが宇宙のまんなかのような渦巻く黒い光がひろがるばかりで 何も見えなかった 男はふいに泪をこぼし その場に蹲った そして天を仰ぐようにしながら かぼそい ことばにならぬ声で うたう ことばにならぬうたが静かに森のなかにひろがっていく 森のなかにたたみこまれた文字がひとつ またひとつと剥がれ落ちていく 森がしだいに薄れていく 男の声がしだいに小さく 掠れていき やがて星が落ちるように途絶えた 森は消え 男は瓦礫の上に横たわっていた どこからか駒鳥がやってきて男の骸にとまり ことばにならぬうたをさえずる
あだし野
あらゆるものは記憶のなかに存在する そこに在るのではない 記憶こそが存在の揺籠である はるか遠くで風が鳴る たとえ亡霊となっても 髑髏となっても そこに記憶があるならばそれは存在なのだ 野の草の陰で ひとつの髑髏がかたかたと鳴る そこへ旅の僧が通りかかる 朽ちかけた井戸の脇に月の光に照らされた亡霊が揺れている もし そこな旅のお方 よほど高貴なお方とお見受けする わしは なんでもへいへいと従うだけが取り柄のしがない足軽 先の戦で親方さまに直々に呼ばれ 頭をおまえに譲るといわれ みるみるうちに立派な甲冑を着せられ 立派な馬に立派な鞘を与えられ 馬子にも衣装とはよく云ったものだわい いざ参られいと云われ いざ敵陣へ しかし馬子にも衣装ではかなうわけもなく あえなく討死 その隙に親方さまは山の向こうへ逃げおおせ 討たれたそれがしは首検分で こやつ偽物とされ この井戸に打ち棄てられる始末 なんと儚しや 儚しや どうぞ経のひとくさりでも唱えてくださいまし 髑髏の眼窩の奥に妖しい光が灯る いや承知と 旅の僧が手をあわせ 念仏をひとくさり すると髑髏の記憶の一切が消え失せ 存在成仏 旅の僧は髑髏の眼窩に生えていた草を抜いてやり また 記憶巡り存在成仏の諸国の旅へ
夜の旋律
どこからか旋律が流れてくる それは風の隙間に紛れるほどのかすかな旋律で どこか哀愁を帯びていた むかしであったか聞き覚えのあるような調べが 大気のなかをたゆたっている 森のなかで聞いたのであったか 星空のしたで聞いたのであったか それとも生まれるまえのことであったか どうにも思いだせない ときおり 躊躇うように旋律が途切れる いったいどこで誰が奏でているのだろう そのとき 一頭の羚羊がとおりかかる 羚羊はふと立ち止まり 耳を立てて夜空を仰いだ そして鼻を鳴らし そのまま森の奥へ消えていった 羚羊もこの調べを聞いたことがあったのだろうか 旋律が少しざわついてくる 胸の奥につかえて壊れそうな 空の端にひっかかってほどけてしまいそうな たよりないざわめきが 木々のあいだをぬけていく 風の匂いが甘酸っぱい そろそろ桃の実がなるころだろうか ふいにあたりが仄かにあかるくなる 橄欖石はふと思いあたった そうだ この旋律は 十六夜の月の昇るときの調べであった
追憶のオルゲル
廃屋のなかの瓦礫に眠るオルゴールが 冷たい月光に照らされる いったいどれだけ月光を浴びたのか だれも数えるものはいない 月が雲で翳ったとき ふいになにものかの記憶が宿る いったいなにものの記憶なのか ほんのり斑の入った白い殻 鏡のように青い空 枯葉に隠れる蚯蚓 鈍色のうねる海 這うように翔る閃光 地の太鼓となり叩きつける雨 あらゆるものを吸い寄せる風の渦 瞬かない星群 ぷつりと途切れる記憶 オルゲルはせめて旋律を奏でようとしたが あいにくもう櫛歯は残っていなかった 透きとおった静寂ばかりがあたりに残響した オルゲルのなかには無数の記憶が宿っていた 人であることも 木であることも 虫であることも 水であることも 石であることもある 行き場を失ってしまった記憶がやってきてオルゲルに宿る 記憶が存在であるならば たったひとつのオルゲルは無数の存在である だがオルゲルはいったいなにものか オルゲルにはオルゲルの記憶がない ただオルゲルであるばかりだった すでに気配の欠片もない廃墟の瓦礫で オルゲルは冷たい月光に照らされている
物質的郷愁へ
それはとうにいのちを終えたというのに まだ両の目をぎらつかせていた 結晶化し物質界にとけこんだはずの目には どこまでも冥い世がうつっていた それはただ無機物がぶつかり犇きあう退屈な世で 花の一輪さえなかった もはや地上には誰のすがたもないだろう それなのに なぜ此処に最後の意とおぼしきものがゆらめいているのか これは涯しのない罪の償いなのか それともいずれやってくる時の予祝なのか もう詞など忘れてしまった もう経など忘れてしまった それでもちろちろと意の火が揺れている なにか円い影が 壁にうつしだされている これはわれの眼窩なのか 日なのか それとも月であるのか 遠い遠いむかし まだ歯も生え揃わない童だったころ 出鱈目で 奔放なウタが口をついていた そのときはまったくわけが分からなかったが あのウタはあらゆる世の祝詞だったのだ ウタには物質的郷愁がふきすさび 日の光も 月の光もただ冷たかった あの鋭利な刃が心臓を抉り 目をくり抜いたはずだが どうにもその後が不分明だった 星から落ちてきた光につつまれると そこは冥い穴のなかで 挿しこまれた竹筒の向こうでうねるような声が響いていた しばらくのあいだ声に耳を澄ませていたが やがてそれは乾涸びた耳には届かなくなった われが物質化する刹那 竹筒の先から一筋の月の光が射した それは宇のはじまりのようであり 極小でありながら極大であり 勾玉のように回っていた すでにすべて物質化し 死をこえたはずであるのに ひと吹きの意が残っていた それもいま消えかかっているが そこにあらわれるのは無辺か それとも底なしの無か おそらくそれを見ることも知ることもないだろう 物質的郷愁のなかでいま意が…